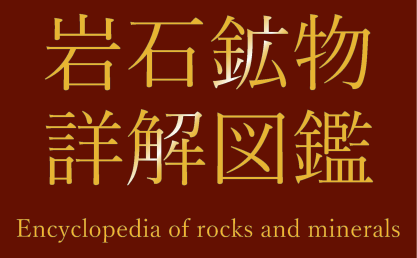礫岩 conglomerate
神奈川県丹沢層群の礫岩
- 礫岩の定義と概要
- 礫岩の分類
- 関連項目
礫岩の定義と概要
地球科学における礫(レキ)とは、径2mm以上の大きさのある程度丸みをもった砕屑物のことを言う。
レキを簡便に説明する際には、「小石」と言われることがあるが、2mm程度の砕屑物は日常会話の用語で言えば「砂」である。
しかし地球科学において砂は2~1/16mmと定義されている。
感覚的には、礫は「荒い"砂"~小石」と思っておけば良いだろう。中には小石よりも更に大きい巨礫(きょれき)が含まれる礫岩もある。
多くの場合、レキは岩片(岩石のカケラ)であるが、単一の鉱物粒である場合も存在する。
レキの隙間は、より細かい粒子である砂や泥によって構成されており、そのようなレキ以外の部分をマトリックス(matrix, 基質)という。
2mm以下の砂や泥は砕屑物のサイズのみによって分類が行われているが、2mm以上の砕屑物は丸みを持っているか否かという形状による分類も加わっている点に注意が必要である。 2mm以上の砕屑物で、ほとんど磨かれておらず角ばった形をしているものからなる岩石は、角礫岩(breccia, ブレッチェア)と呼ばれ礫岩とは区別される。 ただし、慣用的な名称として狭義の(本来の意味での)礫岩と角礫岩をまとめて、広義の礫岩として扱う場合もある。
礫岩の分類
礫岩の分類は主に、 「レキのサイズ」 「レキの構成物や状態(岩石種)」 「基質とレキの関係(岩石組織)」 などによってなされる。 どのような分類方法を採るかは、どのような研究目的で礫岩を扱うかに依存して決定される。 以下に代表的な礫岩の分類方法を挙げる。
レキのサイズによる分類
含まれるレキの大きさによって、礫岩は以下のように細分化される。
- 巨礫岩(boulder conglomerate) - 径256mm以上
- 大礫岩(cobble conglomerate) - 径64mm以上256mm未満
- 中礫岩(pebble conglomerate) - 径4mm以上64mm未満
- 細礫岩(granule conglomerate) - 径2mm以上4mm未満
基質とレキの関係(=岩石組織, テクスチャ)による分類
礫岩中のレキが相互に接触しているものをオルソ礫岩(orthoconglomerate, オルソコングロメレート)という。
オルソ礫岩は斜交層理のような層状構造を一般的に持つ。
一方、礫岩中のレキが互いに接触しておらず、基質内に浮遊するような多量のマトリックスによって互いに分離されている礫岩を、パラ礫岩(パラコングロメレート, paraconglomerate)と呼ぶ。
パラ礫岩は層状構造の不明瞭なものが多く、礫よりも多くの基質を含む。
オルソ礫岩とパラ礫岩との違いは、それらがどのように堆積したかの違いを反映する。
オルソ礫岩は、通常、河川の水流によって堆積した礫岩によって形成される。
パラ礫岩は、土石流堆積物や氷河によって形成された堆積物に見られる。なお、氷河によって形成した礫岩はティライトと呼ばれる。
レキの種類による分類
含まれるレキの岩石種によって、礫岩は大きく「モノミクト礫岩」「ポリミクト礫岩」の2つに分類される。 モノミクト礫岩はほとんど単一種の岩石のレキからなる礫岩で、ポリミクト礫岩は2種類以上の岩石のレキからなる礫岩である。
礫岩の写真